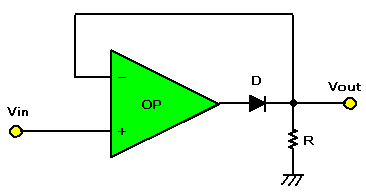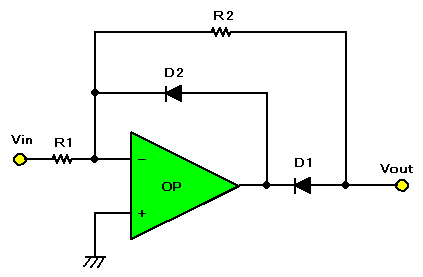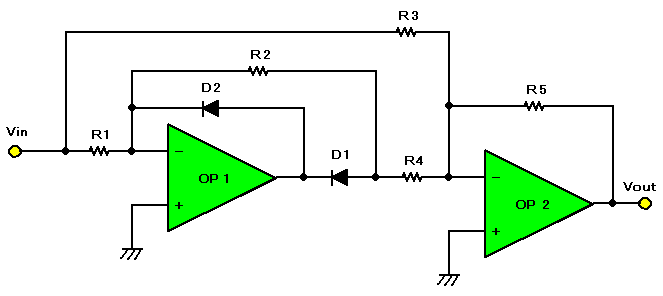検波回路設計のノウハウ
 はじめに
はじめに
狭帯域版スペアナの信号検出部は、ダイオード検波回路を基に設計します。ところで、GigaStスペアナキットや、秋月スペアナキットでは、いずれもTVユニットを流用した構成となっており、ユニットの性能を引き出すことで簡単に出来てしまいます。一方裏を返せばユニットの中身の回路がどうであろうと知る由もありません。狭帯域版スペアナでは、このユニットは使いません。元々このユニットはTV用のため、画一化された帯域性能しか出すことが出来ないからです。ユニットの中を開けて、狭帯域のフィルターをかませる手もありますが、そんな大改造するくらいなら、いっそのこと狭帯域用の回路を自作してしまいましょう。
さて、前置きが長くなりましたが、信号検出部はスペアナの最も心臓部といってもよいぐらいなのです。これまで使用部品についてのノウハウに引き続き、本格的に設計のノウハウに入っていきます。
さて、設計ノウハウのページは、読者にとって一番肝心なところだけに、これからかなりのページ数を割いて連載していきたいと思っています。スペアナだけでなく、一般的な電子工作の設計ノウハウの知識としてでも、是非とも当ホームページで連載される内容をご理解し、電子工作の糧となっていくことを切望いたします。
 (2001.1.9)
(2001.1.9)
ログアンプICを使用する場合には、これらの検波回路は必要ありません。
 非直線性歪・温度特性の改良ノウハウ
非直線性歪・温度特性の改良ノウハウ
ダイオードの使い方のノウハウのところでも掲載した回路ですが、一般的なシングルダイオード検波回路は、最も部品点数が少なくて、簡単な高周波レベルが知りたいときなどに重宝します。しかし欠点は、信号レベルが低いときに非直線性歪を発生することです。非直線性歪みの改良版として、検波ダイオードに予め数十μA程度の電流を流したバイアス検波回路もありますが、温度変動に弱く、精度が要求されるスペアナの信号検出回路には、あまりお勧めできません。そこで、ダイオードとOPアンプを用いた検波[整流]回路(半波/全波)をご紹介します。但し、部品の選定にノウハウがあり、知らないと期待通りの設計が出来ませんので注意して下さい。この回路については、多くの書籍(OPアンプを扱っている大抵の本)に登場してきますが、製作するには実用的な説明が必要に感じます。そこで、SPECTRUM電子工作では、作者の実験データを中心にノウハウ的な情報を連載したいと考えています。
 OPアンプを応用した理想ダイオード検波[整流]回路 (半波整流編)
OPアンプを応用した理想ダイオード検波[整流]回路 (半波整流編)
OPアンプとダイオードを使った半波整流回路には、大きく分けて非反転型と反転型の2種類があります。それぞれ順を追って、その回路構成を示します。OPアンプを扱っている電子回路の本を見たことのある人なら、きっと見覚えのある回路と思います。
ダイオードは非直線性を持っているため、高精度が要求される用途では、ダイオードをOPアンプと組み合わせて使うのがベストでしょう。なにしろ、非線形ダイオードが、OPアンプの力により、理想ダイオードに変身するのですから、これを使わない手はないでしょう。
ここで、理想的なダイオードというのは、ダイオードのもつしきい値電圧VFとその温度変動などが無視できるダイオードの意味で使っています。半端整流回路には、非反転型と反転型の2通りがあります。
(1)非反転型・半波整流回路
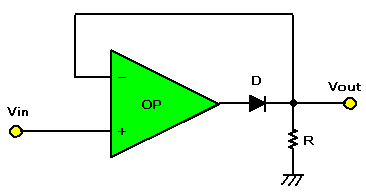 |
| 図1.非反転型・半波整流回路 |
(2)反転型・半波整流回路
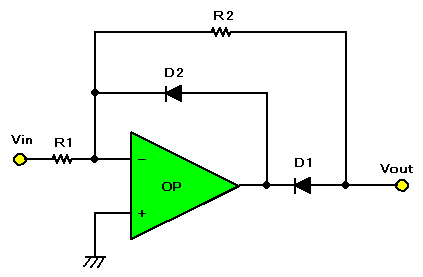 |
| 図2.反転型・半波整流回路 |
 OPアンプを応用した理想ダイオード検波[整流]回路 (全波整流編)
OPアンプを応用した理想ダイオード検波[整流]回路 (全波整流編)
OPアンプとダイオードを使った全波整流回路は、半波整流回路よりも検波効率は良く損失は少ないです。ただし、その分、部品点数が多くなります。半波/全波のどちらの回路を採用するかは、読者の好み次第です。
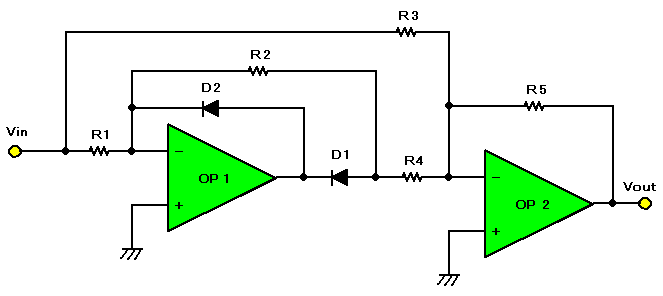 |
| 図3.代表的な全波整流回路 |